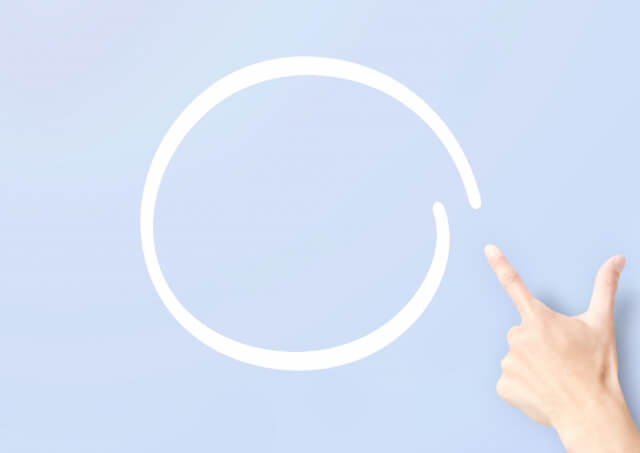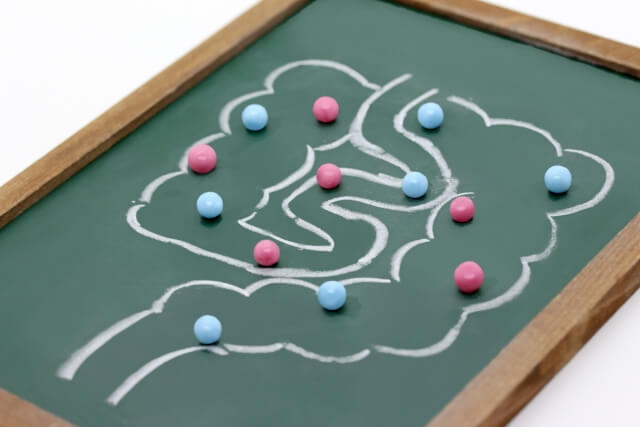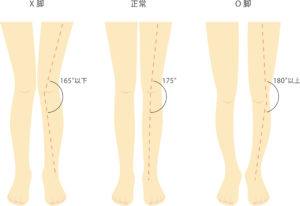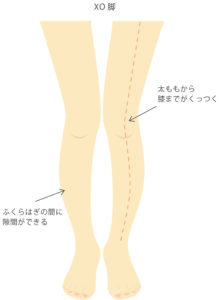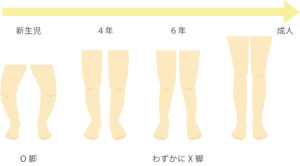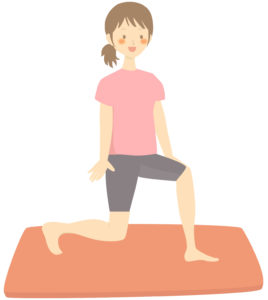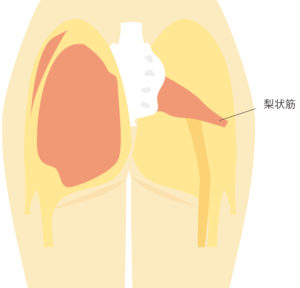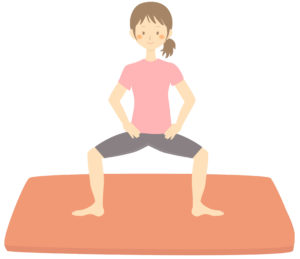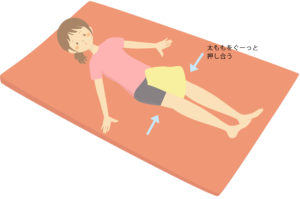受動喫煙は以前から問題視されてきましたが、最近ではがんなどの病気につながるリスクが科学的根拠を持って証明されてきています。
たばこは吸う側だけの問題ではなく周りにいる人たち全員に「受動喫煙」というリスクを与えるので、大切な人を守るためにも望まない受動喫煙をなくす努力をすることが大切です。
改正健康増進法について~正しく理解しよう~

2020年4月1日に「望まない受動喫煙」の防止を図る目的で改定が行われ、特に健康影響の大きい子供や患者に配慮する内容になっています。
改正されて「マナー」から「ルール」に変わった改定健康増進法ですが、何がどのように変わったのでしょうか。
ここではポイントを抑えながら説明していきますので、参考にしてください。
ポイント① 原則屋内禁煙
改正により、様々な施設において屋内は原則禁煙になりました。
対象となる施設は「多数の人が利用する施設」ですが、これは「2人以上の人が利用する施設」のことで、2人以上が同時または入れ替わりで利用する施設を指します。
受動喫煙による健康影響の大きい子供や患者のいる「学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機」については屋外を含めた敷地内が禁煙となり、屋内には喫煙設備を設けることができません。
上記で述べた施設の敷地内では、駐車中の自動車の中でも規制の対象になるので注意しましょう。
ポイント② 屋内で喫煙可能な各種喫煙室
各種喫煙室には、
- 喫煙専用室(〇喫煙 ×飲食)
- 加熱式たばこ専用喫煙室(〇加熱式たばこのみ 〇飲食)
- 喫煙目的室(〇喫煙 〇飲食(主食を除く))
- 喫煙可能室(〇喫煙 〇飲食)
があります。
ポイント③ 既存特定飲食提供施設
既存特定飲食提供施設とは経営規模の小さな飲食店のことで、経営規模の小さな飲食店は経営に影響を及ぼすことが考えられるので、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。
対象となるのは
- 2020年4月1日に既存の飲食店
- 資本金が5,000万円以下
- 客室面積が100㎡以下
の3つすべてに該当する施設になります。
ポイント④ 20歳未満は喫煙エリア立ち入り禁止
20歳未満の者は、喫煙目的でなくても喫煙エリアへの立ち入りが禁止となります。
望まない受動喫煙防止のため、従業員であっても喫煙エリアに入ることはできません。
ポイント⑤ 義務違反時の指導・命令・罰則の適用
違反者には罰則(過料)が課せられることがあり、過料の金額については都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
受動喫煙の対策不備など、違反者には50万円以下の罰則が適用されるので、受動喫煙対策はしっかりと行いましょう。
受動喫煙が体に及ぼす影響~主流煙と副流煙~

喫煙者が吸っている煙だけでなく、たばこから出ている煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールなどの有害物質が含まれています。
たばこを吸わない人は健康面のことを考えてたばこを吸わない生活を送っているのに、街中にたばこの煙が溢れていたら元も子もありません。
ここでは受動喫煙が体にどのような影響を及ぼすのかを、詳しくお話していこうと思います。
受動喫煙のリスクを理解し「望まない受動喫煙」をなくしましょう。
<たばこに含まれる有害物質>
たばこに含まれる三大有害物質は
・ニコチン
・タール
・一酸化炭素
ですが、これ以外にも70種類以上の有害物質・発がん性物質が含まれていて、副流煙には主流煙よりもずっと多くの有害物質が含まれており、これが問題となっています。
ニコチンを摂取することで、
・血管収縮
・血行不良
・動脈硬化
などの体に悪影響な症状を引き起こす可能性が高くなります。
動脈硬化は脳血管疾患や心疾患の原因になるので注意が必要です。
また、タールには発がん性物質や発がんを促進する物質が数十種類以上含まれており、がんの発症に大きく関係しています。
一酸化炭素は酸素を運ぶ機能を阻害し、酸素不足を引き起こしたり動脈硬化を起こしたりする危険性があり、これも脳血管疾患や心疾患の原因となり得ます。
主流煙を1とした場合、副流煙にはニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も多く含まれています。
受動喫煙が「危険」だという認識はまだ薄いですが、これを機に受動喫煙による健康被害をできるだけ減らせるように努めましょう。
受動喫煙との関連①「確実」
受動喫煙との関連が確実(科学的証拠は因果関係を推定するのに十分である)と判定されている疾患には以下ものがあり、科学的根拠を持って示されています。
①がん:肺がん
②循環器の病気:虚血性心疾患、脳卒中
③呼吸器への急性影響:臭気・鼻への刺激感、急性の呼吸器症状(喘息患者・健常者)、急性の呼吸機能低下(喘息患者)
④呼吸器への慢性影響:慢性呼吸器症状、呼吸機能低下、喘息の発症・コントロール悪化、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、乳幼児突然死症候群(SIDS)
受動喫煙による肺がんのリスクは約1.3倍になり、ヘビースモーカーの夫がいる妻は肺がんによる死亡リスクが2倍にも跳ね上がるといわれています。
慢性閉塞性肺疾患においては、いくつかある危険因子の中でも喫煙との関わりが最も深く「たばこ病」とも呼ばれるほどです。
また、心筋梗塞による死亡率は1.3倍になり、受動喫煙をうける人のうち1~3%の人は受動喫煙が原因の心筋梗塞で亡くなっているとのデータもあります。
他にも脳卒中のリスクが約1.3倍、子どもの呼吸器疾患や乳幼児の突然死など多くのリスクが科学的根拠を持って証明されています。
能動喫煙であっても受動喫煙であっても大きな健康被害があるので、自分のことだけでなく家族や周囲の人たちのことも考えることが大切です。
受動喫煙との関連②「可能性あり」
受動喫煙との関連の可能性がある(科学的証拠は因果関係を示唆しているが十分ではない)と判定されているものには以下の疾患があります。
がん:鼻腔・副鼻腔がん、乳がん
たばこを吸わない女性のうち、家庭や職場で受動喫煙を受けていた女性は、受動喫煙を受けていなかった女性に比べて乳がんのリスクが2.6倍ほど高くなる可能性があります。
喫煙の有無で乳がんの生存率が大きく変わってくるともされており、10年生存率は吸わない人で90%、喫煙者では60~70%だといわれています。
受動喫煙もこのように影響があるかもしれないので、積極的な禁煙や受動喫煙の防止に努めましょう。
受動喫煙をなくすためには~禁煙と分煙~

国民の8割以上は非喫煙者で、受動喫煙を受けなければ肺がんや脳卒中などの疾患による死亡者を、年間15,000人減らすことができるといわれています。
受動喫煙を受けることのない日常が構築されることで多くの人の命を守れる訳ですから、1人ひとりが意識を持って社会生活を営む必要があります。
三次喫煙(サードハンド・スモーク)とは
受動喫煙には三次喫煙(サードハンド・スモーク)というものがあり、煙を直接吸い込まなくても家具や壁紙、カーテン、絨毯、車のシート、エアコンの内部などに付着し、徐々に空気中に浮遊します。
たばこの煙がない空間でも「たばこの臭いがする」と思えば三次喫煙の可能性があり、分煙をしていても喫煙者が髪の毛や衣服などに付着した有害物質を持ち運ぶことで、周りの人は知らないうちに三次喫煙の影響を受けることになります。
たばこの煙にさらされたコットンのクロスから、私たち人間がどれくらいの影響を受けるかを測定したカリフォルニア大学の研究によると、受動喫煙に比べてニコチンは子どもで6.8倍以上、成人で24倍以上という結果が出ています。
発がん性のあるニトロソアミンについては、子どもで16倍以上、成人で56倍以上という恐ろしい数字が出ています。
では、このような受動喫煙を防ぐ為にはどうすれば良いのでしょうか。
受動喫煙から身を守るために
受動喫煙の危険性から自分や家族、友人などを守るための唯一の方法は「禁煙」しかありません。
最近では「喫煙率ゼロ」の取り組みをしている会社や団体も増えてきましたが、成人がたばこを吸うことは法律で禁止されているわけではないので、完全になくすことが難しいのが現状です。
喫煙者が周囲に気遣うのは最低限のマナーですが、たばこを吸わない人も受動喫煙から自らの体を守りましょう。
たばこを吸わない人が受動喫煙を防ぐには、たばこの煙のない空間で過ごすことが第一です。
例えば、
- 全面禁煙の施設の利用
- 個室のある飲食店
- たばこを吸い終わった直後の人に近づかない
などが挙げられます。
密閉されたビルなどでは完璧な無煙環境を作ることが困難です。
完全分煙でも屋内に喫煙スペースがあれば受動喫煙のリスクはゼロにはならないので、ビル全体(屋内全体)が禁煙の施設を利用するようにしましょう。
また、タバコを吸い終わった直後の人は口や肺の中に有害物質が残留しているので、時間をおいてから接するようにしましょう。
逆に、たばこを吸う側の人は人と接する直前にはたばこを吸わないように心がけましょう。
いきなり禁煙するのは難しいかもしれませんが、大切な人のことを考えて受動喫煙防止に取り組みましょう。
受動喫煙を防止するための「禁煙」のコツ

受動喫煙は大切な家族を危険にさらす可能性がありますし、自分の知らない誰かが自分の知らないところで苦しんでいる可能性もあります。
受動喫煙をなくすには禁煙しか方法がないので、これを機に禁煙に取り組んでみませんか?
ここでは禁煙を考えている人のために「禁煙できるコツ」を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
コツ① 禁煙開始日を決める
「休日は家族と過ごす時間が長いのであまり吸わない」という人は休日に、「会社は禁煙なので平日はほとんど吸わない」という人は平日に設定することで、スムーズに開始することができます。
また、仕事でストレスが溜まっていたり忙しかったりするときは避け、心や時間にゆとりがある時に設定するのが無難です。
「明日から禁煙しよう」と思ってもすぐに禁煙するのは難しいですし、きっと多くの人は失敗した経験があると思います。
「次のプロジェクトが終わってから」「繁忙期が終わってから」など、最低でも1~2週間程度の期間をあけて禁煙開始日を設定しましょう。
コツ② 周りの人に宣言する
これはダイエットでも同じですが、1人でこっそり開始してもなかなか長続きせず失敗する可能性が高いです。
失敗しても誰からも責められない・強い意志が必要ない状況では自分に甘くなりがちなので、強い意志を継続することが難しくなります。
禁煙には強い意志が必要になってくるので、禁煙を決意して開始日を設定したら周りの人たちに禁煙を宣言して協力してもらいましょう。
たばこを持ち歩かなくなっても、どうしても「吸いたい」という欲求が生まれる時があります。
禁煙を宣言していない場合は、同僚などに「1本ちょうだい」と言えばもらうことができますし、友人を待たせてコンビニに買いに行くこともできるので、このような状況を作らないためにも周りに宣言して「禁煙しやすい環境」を作っておく必要があります。
コツ③ たばこの代替を作る
朝起きてすぐ、毎食後、お酒の席など、吸うことが当たり前=ルーティンになっている場合は、その時間・その環境に置かれると「吸いたい」という気持ちが湧いてくると思います。
このような時は、
- 水を飲む
- ガムをかむ
- 歯磨きをする
などのたばこの「代替」を作ると、吸いたい気持ちをうまくコントロールできるようになります。
朝起きたらすぐに水を飲み、食後は歯磨きをし、お酒の席で吸いたくなったらガムを噛むようにするなど、たばこの代わりになるものを考えましょう。
ガム以外にも、噛み応えのあるもの(するめ、干し昆布、ビーフジャーキーなど)で口寂しさをしのぎましょう。
受動喫煙防止以外にも!「禁煙」のメリット

禁煙することで受動喫煙がなくなるとお話しましたが、受動喫煙がなくなるだけでなく自分自身にも多くのメリットあがります。
「たばこはこんなにも多くのリスクがある」というリスクにばかり目を向けるのではなく、禁煙することによる多くのメリットを知れば、おのずと禁煙する意味が見えてくると思います。
メリット① 1年で虚血性心疾患のリスクが喫煙者の半分に減少
たばこを20分吸わないでいると血圧や脈拍が正常に戻り、8時間で血液中の酸素が正常値まで増加します。
このように、吸わない時間が長くなることで病気のリスクが減り、10~15年経つと脳卒中や肺がんのリスクが吸わない人と同じくらいになると言われています。
メリット② 時間やお金に余裕ができる
1日20本(1本5分)たばこを吸う人では、1日で1時間40分、1ヶ月で2日と2時間、1年で25日分の時間を喫煙に使っている計算になります。
また、1箱500円のたばこだと1ヶ月で1万5千円、1年で18万円、10年で180万円も使っていることになります。
たばこを吸わなくなればこれだけ多くの時間とお金を使わずに済むので、その分自分の時間を作ったり旅行に行ったりする余裕ができます。
メリット③ 心身ともに元気になる
禁煙するとイライラしたりストレスが溜まったりすると思われていますが、実は禁煙することでストレスが軽減して精神的健康度が改善すると言われています。
他にも、肌がきれいになる・体力が戻る・寝つきや寝起きが良くなるなどのメリットが多くありますので、疲れがなかなか取れない人やストレスが溜まっている人は禁煙することで体調の回復を図りましょう。
まとめ【望まない受動喫煙をなくすためにも禁煙を!】
- 受動喫煙防止は「マナー」から「ルール」になり、違反すれば50万円以下の罰則も
- 受動喫煙をなくすためには禁煙しかない
- 受動喫煙は能動喫煙よりもリスクが高い
- 禁煙すれば10~15年で脳卒中や肺がんのリスクが吸わない人と同等に
受動喫煙に対する取り組みは、これからもっと厳しくなっていくと思います。
たばこの煙は「百害あって一利なし」ですから、望まない受動喫煙をなくすために社会全体で取り組みましょう。